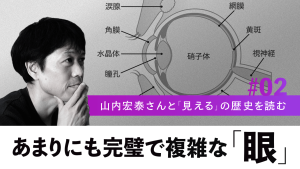Writer:山内宏泰
2020/08/30
眼はどうして生まれたか〜生命史を画する「眼の出現」〜
実は、39億年前、地球上に生命が誕生したそのときには、まだ生物に「眼」はありませんでした。
私たち人間も含めた生命体が、種を存続させるために、光を感知する器官を発達させ、映像を認識する「眼」を自分の体に備えることで、「賢く」生きることが可能になります。
美術・文学に造詣が深い山内宏泰編集長と、「見える」の歴史を探ります。
太平の眠りを覚ました「眼」
光あれ−−
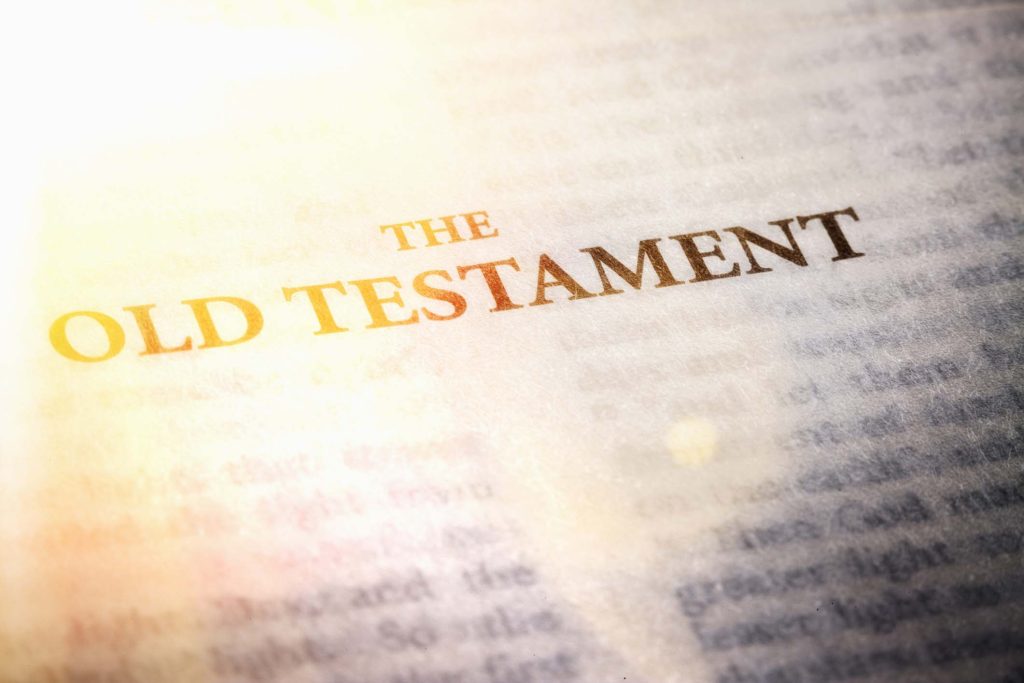
と神がひと声かけたことで、この世のすべてが始まった。そう旧約聖書は説いている。
これを「単なる神話でしょ?」などと片付けるのは得策じゃない。最初に光だけがあったという見解は、生物史学的にもそのまま賛同されるものなのだから。
46億年前に地球が誕生したとき、そこにはまちがいなく、太陽から絶え間なく降り注ぐ光だけが存在した。
しばらくすると、光に照らされた地球上に、生命が誕生した。39億年前に起きた画期的な出来事である。
ただしその後長らくは、バクテリアや藻類、単細胞動物のみが海を漂うばかり。変わり映えのしない、静かで穏やかな時間が、延々と過ぎていった。
ようやく10億年ほど前になって、多細胞生物が現れる。海綿動物の類で、いまでいうナマコみたいな動物だった。ナマコやクラゲに似た、ごく限られた種類の生物ばかりが海に満ち満ちた。
そして約5億4千万年前、大変化が訪れる。地球上に突如として、多種多様な生物が出現することとなったのだ。
それまでは、フニャフニャと小さく頼りない生きものばかりだったのが、いきなり歯や触手や爪、頑丈なアゴなどを持ち、前世代からしてみればエイリアンのような、いや後世の私たちから見てもじゅうぶんに奇態な動物たちが、海中を大挙行き交うようになった。
「カンブリア紀の大爆発」と呼ばれる現象だ。
地球の生きものはこの時期に圧倒的に種類が増え、大きくなり硬くなり、そして賢くなった。何億年ののちにヒトという種が生まれる素地は、ここでできた。
生物史のハイライトと言っていいカンブリア紀の大爆発。これをもたらした大きな要因とされるのが、眼の存在である。
動物に眼があるのは当たり前では? と思うかもしれないけれど、そうじゃない。
この時期以前の生物には一切、眼というものがなかった。地球上に眼というもの自体が存在しなかったのだ。
それなのに、カンブリア紀の地層から出てくる化石には、眼のかたちがはっきりと刻印されている。
どうやら眼が誕生したのはこのカンブリア紀であり、眼の出現こそ生物の多様性と深い関わりがあるようなのだ。
生き延びるための最大の武器に、光を採用

カンブリア紀に眼が生まれた理由と、「大爆発」への影響とはどんなものだったか。
話の前提として、あらゆる生命体が従っている基本原則をふりかえっておくと、こういうことになる。
個体としては、生き延びること。それが何にも勝る至上命題である。そのためには、他者に食べられないこと。そして他者を食べることが必要となる。
種族としては、殖え続けることが唯一最大の目標となる。自分たちの生息場所を確保し持続させるために、環境変化に適応しながら、居場所を防衛することに専心すべしだ。
生命体が生き延び、殖え続けるうえで、大いに活用してきたものは光である。太陽光は地球のどこにもあって、あらゆる生物が外界から受ける刺激としては、いつの時代にも最大のものだったのだ。
だから生物は古くから、生き延びる手段のひとつとして、光を感知する器官を発達させてきた。最初は単に明るさを感じ取る感知器官ができた。単細胞生物でもすでに光を感じ取り、それによってみずからの運動の方向を決めていた。
ただし、それら光の感知器官は、眼とは呼べない。外界から光の刺激を受けて体内で何らかの像を結び、周囲の環境を映像として把握できてこそ、眼である。映像を形成する能力、つまりは視覚を生物にもたらすのが眼という存在ということだ。
光を感受する眼点は、多くの生物の体内で長い時間をかけて進化してきた。
そうしてカンブリア紀に、着々と前進してきた成果が花開いた。外界の像を結べる眼の構造はひじょうに複雑だけど、おそらくは何かしらのプラス要因も作用して−−その時期に太陽から届く光量が増したのか、海水の濃度や透明度に変化があったのか……、定かではない−−、一挙に眼の進化が成ったのだ。
視覚が生物の生き方もかたちも変えた
眼という器官を持ち、視覚を宿した生物は、生存競争のうえで圧倒的な優位に立った。
たいていの動物は捕食者であり被食者でもあるわけだけれど、生命が眼を持つ以前の捕食行動というのは、ずいぶん行き当たりばったりの非効率なものだった。
それはそうだ、視覚がないのだから、せいぜいイソギンチャクみたいな生物が触手を水中に漂わせて、そこに触れたものを捕獲するくらいしかできない。食う・食われる関係といっても、かなり牧歌的だ。
眼を持つ生物が出現すると、事情は一変する。離れたところからでも、獲物のかたち、色、居場所、行動がすべてわかってしまう。眼を持つ捕食者は、あとは移動能力を進化させていけば、ほぼ無敵になれそうである。
もちろん被食者として狙われる側も、黙って食われているだけじゃない。視覚に対抗するためにさまざまな進化を遂げるようになる。身体の表面を容易に食べられないほど硬くしたり、派手な警告色で彩ったり、岩の隙間や砂中に隠れられるよう変形したり、周囲と同化するよう身体の質感や色合いを変えてみたり……。
先にカンブリア紀には生物の種類が増え、大きくなり硬くなり、そして賢くなったと述べたのは、こうした事情による。
活発な捕食と、それに対する対抗策によって、生物は多様化し、新しい能力が開発されていった。
哺乳類、そして人類へ連なる生物種もこの大競争の中から生じてきたのだった。なるほど競争が変化と進歩を生むというのは、6億年前からいまに至るまで変わらぬ真理のようである。
生命に最初の大きな変化と進化をもたらしたのは、眼であり視覚であり、「見る・見られる」という関係性だった。
こののちもヒトが現在の位置へ行き着くまでには、眼、視覚、見る・見られるが大きな役割を担うこととなる。
その様子を、しばし追いかけてみよう。
著者紹介 About Writer

- 山内宏泰
- ライター。美術、写真、文芸について造詣が深い。
著書に『写真のフクシュウ 荒木経惟の言葉』(パイインターナショナル)『写真のフクシュウ 森山大道の言葉』(パイインターナショナル)『上野に行って2時間で学びなおす西洋絵画史』(星海社新書)など。
「見える未来文化研究所」の共同編集長。
この連載について About Serial
山内宏泰さんと「見える」の歴史を読む
美術・文学に造詣が深い山内宏泰編集長と、「見える」の歴史を探ります。
- この記事をシェアする
-